
NEWSニュース
![]()
![]()
アトツギ社長のノウハウで挑む、水産養殖業の再成長
______________________________________________
静岡県が運営するイノベーション拠点「SHIP」では、地域における起業支援や新規事業開発、DX支援、
デジタル人材やイノベーション人材の育成を目的とした多様な支援を行っています。
本シリーズでは、SHIPを活用し成長・発展を遂げた起業家や企業、プロジェクトの事例を通じて、
SHIPが果たす役割と効果をご紹介いたします。
皆さまの今後のSHIP活用のヒントになれば幸いです。ぜひご覧ください。
______________________________________________
アトツギ社長のノウハウで挑む、水産養殖業の再成長
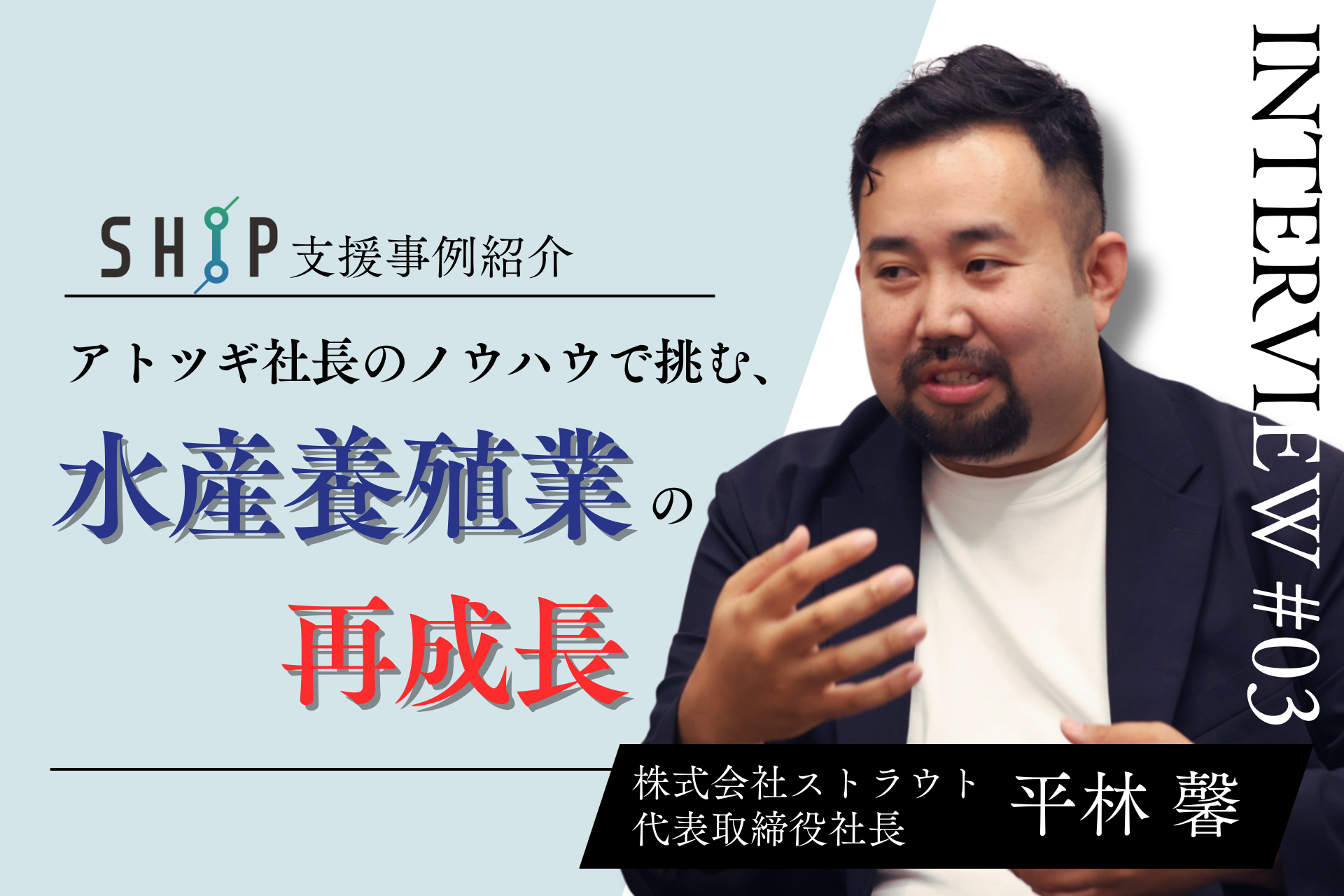
地域資源の有効活用とテクノロジーの融合で水産養殖業の再成長に挑戦する株式会社ストラウト。
同社は現在、静岡市清水区の自社陸上養殖拠点にて養殖運用技術を磨くとともに、
AI・IoT養殖技術の研究開発も行っています。これにより「IT×陸上養殖」を実践した
新規開発・運営事業を展開し、国内外で持続的な陸上養殖の推進を目指しています。
今回、株式会社ストラウト代表取締役社長 平林馨さんにSHIPとの出会いや
活用方法、事業への想いを伺いました。
内水面養殖業衰退の危機
日本は今、先人たちが築いてきた養殖業衰退の危機に直面しています。事実、
異常気象等で事業が儲かりづらくなっていたり、後継ぎがいないといった理由で、
毎年いくつかの養殖場が廃業しています。
たしかに、自然とともに生きるというのはとても大変なことです。
異常気象や病気などで、大切な魚を廃棄しなければならない時もあります。
しかし私は、地域資源を最大限に活用することで、内水面養殖業の再生と成長を
実現できると信じています。
そこで私は2020年、株式会社ストラウトを設立しました。
弊社では、全国に陸上養殖場を増やす取り組みに力を入れています。
そしていずれは、蓄積されたノウハウをAIに学習させることで、人材不足の
日本でも安定して美味しい魚を作れる仕組みを構築することを目指しています。
残したい風景があったから
ストラウト創業の原点には、私が代表を務めているもう一つの会社、
有限会社柴崎養鱒場があります。
柴崎養鱒場は60年以上続く歴史の長い魚の養殖場です。静岡県富士宮市と
宮城県白石市にて、地下水を利用してニジマスやイワナ、銀鮭を養殖しています。
柴崎養鱒場は、もともと私の祖父が経営していました。私自身は東京で
生まれ育ちましたが、20歳の時に祖父から「事業を継いでほしい」と言われました。
それからは経営のことばかり考えて生きてきました。
大学卒業後は食品系の商社に入社し、営業する技術を学びました。
また、働きつつMBAを取得、一年後には、M&Aや事業再生をやっている
コンサルティングファームに入社しました。ここでは、経営のノウハウや傾いた事業を
立て直す術を学びました。さらに3年後、ビジネススクール(MBA)に通いながら
外資系コンサルに入り、大手企業との関わり方を学びました。
今思い返すと、私の20代は経営技術を身につけるためにあったと言えるかもしれません。
こうして2019年7月、柴崎養鱒場に入社しました。入社から4ヶ月後、代表に就任しました。
想像はしていましたが、入社当時の柴崎養鱒場は火の車でした。
それでも、この事業を終わらせたくないと強く思っています。理由は非常にシンプル。
養殖をやっている実家や養鱒場のある富士宮の風景がなくなってしまうのが寂しかったからです。
私にとっては、柴崎養鱒場は人生をかけて残したい風景の一つでした。
ピッチのブラッシュアップを支援
ストラウトが陸上養殖場を増やす取り組みを始める前に、大きな準備段階がありました。
会社設立当初、力を入れていたのが「養殖DX」でした。
養殖業を改善するためにはどうすればよいかと考えたとき、まず思いついたのはセンシングでした。
センサーを用いて水質をリアルタイムに把握し、それを過去のデータと照合して養殖場の状態や病気を
予測することができるのではないかと考え、養殖アプリ「UMIDaS(ウミダス)」を開発しました。
このUMIDaSをピッチの中心に添えて挑んだのが、静岡県主催スタートアップビジネスプランコンテスト
「WAVES」でした。また、このWAVESのキックオフで訪れたことをきっかけにSHIPを知り、
私の人生を大きく左右するSHIP相談員の北川さんに出会うことができました。
北川さんにはビジネスプランコンテストの資料作成や審査員の印象に残る術など、ピッチの
ブラッシュアップをサポートしていただきました。おかげで、WAVESでは3rdグランプリを
受賞することができました。さらに養殖DXを基軸に、さまざまなアクセラレーションプログラムに
挑戦することができました。
養殖DXからの転換

しかし養殖アプリの紹介を重ねていくうちに、「この方向性は私たちの目指すビジョンに
クリティカルではないのでは?」と考えるようになっていきました。
理由は3つあります。
1つ目は、センシングなどの技術は、すでに実践している人たちがいたためです。
水産庁の資料によると、陸上養殖事業に参入する大手企業が増えているものの、
収益が伸び悩んで撤退していくケースが散見されました。
つまり、収益が出せないのは養殖DXなどの技術的なレベル差だけではありません。
テクノロジー以前の問題として、単純に「良い魚が作れないから」ではないかと考えました。
2つ目は、養殖場の状況は場所によって千差万別であり、DXの横展開が根本的に
困難だと思ったためです。たとえば、あるアクセラレータープログラムを通じて
全国の養殖場を回らせていただいたこともありますが、これを押し売りしたところで、
養殖業者のためにはならないと思いました。
3つ目は、日頃お世話になっている方から「このビジネスに将来性はないよ」と指摘されたことです。
それも、スタートアップピッチイベント当日ですよ(笑)
驚きはしましたが、「君だって本当はやりたくないんでしょ? 事業の強みが活かされていないよ」
と言われ、納得してしまう自分がいました。
資金調達をする理由を突き詰める
ちょうどその時期、資金調達が思うように進まなくなっていました。
このまま前進するか、どこかで大きく舵を切るか、一人で悩む日々を送っていました。
私の焦りを感じ取ってくれたのでしょう、北川さんは忙しい中でも熱心に話を聞いてくださいました。
そして「資金調達は、しなくてもよいならしないほうがよい。それでもやるなら、根源的な理由を
もっと突き詰めるべきです」といったアドバイスをくださいました。
なぜ資金調達が上手くいかないのか。需要があれば、自然と出資者の興味を引くはずではないか。
つまるところ、PSF(Problem-Solution Fit、顧客課題と解決策の合致)していないのではないか——
北川さんの言葉にはもっと深い意味があったのかもしれませんが、私はそう感じ、自分たちの
得意分野を活用する道を模索しました。
世の中、気候変動の影響を受けて海面環境を読み解くことはますます困難になってきています。
そこで柴崎養鱒場も含め、私たちが長年積み上げてきた内水面養殖と陸上養殖のノウハウが
役に立つのではないかと考えるようになりました。
このように、検討したアイデアを北川さんにお話ししたところ「これは可能性を感じます!」
と言っていただけました。それから北川さんには、事業の成長戦略や課題の洗い出しなど、
さまざまな方面でサポートしていただきました。多い時はほぼ毎日のように相談させてもらいました。
理解されないビジネスほど社会にインパクトを与える
北川さんにはベンチャーキャピタル(以下、VC)へのアプローチでもお世話になりました。
もともとVCへの提案は予定はありませんでした。
AIや再生可能エネルギーのようなトレンドの事業ならいざしらず、養殖のような
華やかさに欠ける業界ではVCの興味を引けるとは思えなかったからです。
しかし北川さんは、渋っている私の背中を押してくださいました。ありがたいことに
多くのVCを紹介してくださったのですが、まさかの全滅。出資は受けられませんでした。
少し申し訳なく思いましたが、北川さんはショックを受けている様子もなく
「理解されないビジネスほど社会にインパクトを与えるものです」と言ってくれました。

その一言でどれほど救われたことか。世の中、うまくいくことばかりではありません。
何が成功するかなんて誰にもわからない。それでも最後までやり抜こう。
できることはやっていこうと教えられた気がしました。
その後もVCへのアプローチは積極的に続けています。また、事業の方向性を見直し、
全国で陸上養殖場を作る事業へ舵をきっていきました。
アトツギだからこそ挑戦する
「なぜそこまで貪欲に挑戦をするのか?」と聞かれることもあります。
事業承継した新社長の多くは、事業を継続させることに精一杯で、なかなか挑戦をしないものです。
しかし私はむしろ逆、跡継ぎでありすでに事業の軸を持っているからこそ挑戦しなければ
いけないと考えています。勝てるゲームだけをやっていては非連続的な成長ができませんから。
だからといって、変えてはいけないものがあるのも事実。とくに地域ビジネスにおいて、
長年続いてきた事業は堅実に守り続ける必要があると考えます。世間の流行や一時的な
トレンドに乗って大きな転換を図ることは、しばしば予期しないリスクを生むことになります。
たとえばうちの養殖場では長い間、大きなニジマスと小さなニジマスの2つのサイズを
養殖していましたが、コンサルタントの方から「大きなニジマス一本に絞ったほうがいい」
という助言をもらいました。
たしかに、世間のニーズは大きなニジマスに傾いていましたし、経営における「選択と集中」
という点でこの判断は間違っていません。しかし、私は提案を受け入れませんでした。
するとその直後、コロナ禍によるバーベキュー需要から小さなニジマスが人気となったんです。
あそこで小さなニジマスを縮小しないで本当に良かったと思います。このように、どこかで必ず
揺り戻しがあるんです。時代の揺らぎに対応しつつ、変えないところは変えないこと。
その見極めが重要です。
GRIT力と失敗からの学び
私がビジネスをするうえで大切にしている考えが2つあります。
一つは、GRIT(グリット)力です。
GRIT力とは簡単に言うと「どんな困難があっても諦めずにやり抜く力」のこと。
ビジネスで成功するには、才能や知識だけではなく、困難に直面しても諦めずに
目標に向かう姿勢が求められると考えます。
もう一つは「成功はアート、失敗はサイエンス」という考え。
これはOWNDAYSの社長(現・会長)、田中修治さんの言葉です。成功の原因は複雑で
多岐にわたるため、理屈や法則で説明できるものではありません。一方で、失敗の
原因は科学のように分析することができるという意味です。
スタートアップにおいては「運が向かないこと」が多々あります。
どん底まで落ちていくことも珍しくないでしょう。とくに事業アイデアを形にし、
市場テストを始めるシード期にはあるあるです。
私だって例外ではありません。何度も挫折しそうになりました。今でも挫折しそうになります。
でも、そこで諦めない。どんな状況でも食らいつこうと覚悟しているからこそ、
今があるのだと確信しています。
ビジネスをするうえで、多少の失敗は避けられないものです。
しかし、失敗は自分の限界や不足を知る貴重なチャンスでもあります。
失敗を分析し、次の一手に活かすことができる人が、成功に近づけるのではないでしょうか。

専門家の揃ったSHIP
相談のしやすさがSHIPの魅力です。とくに私の場合、相談員さんに若い方が多く、
自分と年齢が近かったからフラットに会話ができたところもあります。
何より、SHIPには事業経験や専門的な知識を持った方々が揃っています。
事業施策や資金調達におけるアドバイスでしたら、銀行の担当者や会計士のような
金融関係者からもしてもらうことができます。そういった方々からのアドバイスは
金融知識が豊かで参考になります。
一方、エクイティファイナンスのような資本政策に関わる分野は将来展開にも関わるため、
金融知識以外にも起業家や事業に対しての理解が必要です。そうした領域で納得感のある
助言をもらえるアドバイザーはそう多くはありません。
ところがSHIPにはそれを相談できる人がいるんです。
可能なら、SHIPの相談員さんをうちの会社に引き抜きたいくらいです(笑)
成長を見せることが恩返し
目指す先は、陸上養殖だけで売り上げ100億円です。
すでに全国数カ所で陸上養殖場の建設プロジェクトが動いています。同時に、養鱒業界も
巻き込んで海外への進出も視野に入れて動き出しています。今後は、世界中で美味しい
ニジマスや魚を食べられるようにしていきたいです。
そんな中でも、SHIPは積極的に利用していきたいですね。
ここに来れば新たな展開がある——そんな期待を抱かせてくれる場所です。
たとえば、今日も立ち話の中で「ある海外政府と仕事をしたいと思っている」とこぼしたら、
「現地の人材を紹介できるかもしれない」と言っていただけました。
そういう人材の獲得の話までできてしまったんです。
本当に、感謝してもしきれません。だから私はこうやって、自分の成長を見せることで
SHIPに恩返しとさせてもらっています。今後も、私の成長を見守っていただければ嬉しいです。
私のように「新たな事業を立ち上げたい」とか「世界に飛び出したい」と考えている方々は、
ぜひSHIPの相談員の方に話してみてください。

___________________________________________
【SHIP公式SNSのご案内】
直近のイベント情報、本日のイベント有無、ご支援情報、SHIPの日常の様子などを配信中!
ぜひ、フォロー&ご登録をよろしくお願いいたします!
▶LINE:https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=314zbucp
▶Facebook:https://www.facebook.com/share/knCmY2HNGv4Lmvrz/?mibextid=LQQJ4d
___________________________________________